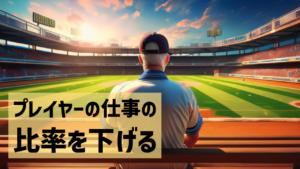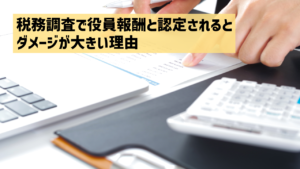役員貸付金が発生する理由は以前のブログでお伝えしましたが、役員貸付金そのものが与える影響についてもお伝えしておきます。どこかのタイミングで役員貸付金を解消したほうがよいです。
対金融機関 決算書の見栄え
役員貸付金そのものは発生してしまうことがあり得ます。問題はその認識があるかどうかと、解消する手立てを打っているかどうか。
金融機関に決算書を見せる機会というのは中小企業の場合は比較的あります。
特に融資を受けている、もしくは受けようとしている場合には決算書ベースでの事業内容の把握が金融機関では必ず行われますので決算書を見せてくださいと言われるわけです。
このときに、役員貸付金があるとどう捉えられるか。
会社の資産や資金を役員(この場合は社長とします)が使っていると見做されるわけです。
いろんな発生原因があるにせよ、金融機関に見せる決算書ではプラス要素にはなりえません。
仮払金にすればいいという経営者もいますが結局のところ中身の確認が入るだけで実態としては同じであれば金融機関側で仮払金=役員貸付金として認識されます。
あとは借入をする際にマイナス評価になる要因としては、役員貸付金があるとどうしても「ここの社長は会社の金をプライベートに使ってしまうようだから貸付したらそのお金も流れる可能性がある」と捉えられる可能性があることです。
金融機関としては返してもらえないリスクが一番避けたいことでしょうし、特に貸したお金の使い方には非常に敏感です。
いわゆる資金使途違反と言って融資の目的外の資金使途(お金の使いみち)は契約違反とされており、新規融資の停止、一括返済を求められる可能性があります。
対金融機関においてはマイナスイメージしかない役員貸付金ですので、もし勘定科目に計上されている場合には解消するために何をしているかは説明しておきたいところです。
対税務調査
税務調査にも影響を及ぼすことがあります。
法人は利益を出していくことを目的としているのでタダで何かをすることはないと考えておいてもらうと理解しやすいです。
役員貸付金については文字通り会社から役員への貸付ですのでタダでお金を貸している状態に見えます。
そうするとお金を貸しているのであれば利息を取りなさい、と税務調査で指摘される可能性があります。
また役員個人の支出であれば役員報酬ではないか、役員賞与ではないかと指摘される可能性もあります。
いずれの場合も役員貸付金があることでの影響と言えるでしょう。
もし役員賞与と認定されてしまうと、役員報酬の損金算入要件を満たさないので経費計上にはならず法人税が増えます。また源泉所得税の徴収も指摘されるとさらに役員報酬から源泉所得税を徴収して納付し追徴もあります。
影響としてはかなり大きくなりますので少なくとも役員貸付金があってプラスの影響はないですし、もし計上されていても対応できることをしておきたいところです。
まとめ
役員貸付金は会社のお金を使うことでもそうですし、個人の支出でカードを切ってその支払を法人で行ったりすると発生します。
ポジティブに捉えられることはないので発生しないように、また発生したときの対応も確認しておきましょう。