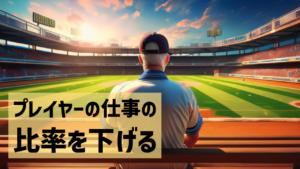役員借入金がある中小企業のサポートをしていると、「役員借入金を減らせないか」というのは提案事項として考えたいことの一つになります。
例えば、その社長の相続財産になりうるというのがまず第一に考えたいところですし、可能であれば減らしておきたいと思うものです。
今回は、役員借入金を債務免除(債権放棄)する際のデメリットと、ほかに取れる対策がないか考えてみます。
役員借入金の債務免除とは
会社から見ると役員(多くの場合が社長)から会社がお金を借りている勘定科目を指します。
実際に役員から会社がお金を借りているケースもあるでしょう。中小企業だと資金繰りに窮したとき、少しキャッシュを増やしておきたいときなど、金融機関からの借り入れまでの間に、先に社長からお金を入れることはよくあります。
大切な会社がうまく回りそうではない、という場面でも中小企業の社長は、いわば一時的に(その時はそう思っていたとして)お金を会社に入れることはしばしばあるものです。会社がつぶれるくらいなら身銭を切って当座をしのぐというイメージです。
そういったことも役員借入金の発生要因の一つですが、ほかにも会社が払うべき経費などを役員が立て替えているときにも役員借入金が発生します。
当座しのぎで立て替えていたとして、会社にお金が増えてきたら返済してもらおうというのは普通に考えることだと思います。そうこうしているうちに、「会社からお金を返してもらうと少し会社の資金繰り的にきついかも」となってしまって、結局返してもらえないまま数年、十数年が経つということもあり得るわけです。
こうして膨らんできた役員借入金ですが、解消しようと思うと実際に会社から役員にお金を支払うか、債務免除という方法が選択肢となります。
債務免除(役員側から見ると債権放棄)は簡単に言うと、役員との合意で「もう返してもらわなくてもよい」という状態にするわけです。
会社側は債務を免除してもらっているわけですので、債務免除益が計上されますが、赤字が続いて欠損が繰り越されている場合には、実際には課税がないということも可能性としてはあります。
役員から見ると、要は貸し倒れているわけです。
ほかにも対策としてはありますが、債務免除が手っ取り早いこともあって選択されがちです。
ただし、債務免除の一番のデメリットと言えるのは「返してもらえなくなる」ということでしょう。
役員からすると貸し倒れてしまったわけですから回収できないのと同じ状態ですし、実質的に「返してもらわなくてよい」という処理になってしまいます。
返してもらえるなら返してもらいたいというのが一般的な感覚だと思いますので、そこが気になるのであれば、ほかの対策を検討するのがおすすめです。
債務免除以外の対策
債務免除以外の対策として2つ取り上げてみます。
1. 役員報酬の減額による返済
まず一つが役員報酬を減額して、その減った分を役員借入金の返済で充当するという形です。
例えば、月に50万円の役員報酬を受け取っている場合に、これを30万円に決算のタイミングで減額します。20万円の役員報酬減額となってしまいますが、その20万円を会社から役員に役員借入金の返済として充当するわけです。
社会保険料も額面が減ることで(50万円→30万円)、減額されますので、その分を見越して役員借入金の返済金額を調整することもよいでしょう。会社負担分も減りますので、額面50万円で変わらないように見えるかもしれませんが、会社の資金繰りも改善する可能性は高いです。
この選択肢を取ろうと思うと、役員報酬をある程度取っているほうが効果としては高いです。というのも、結局は役員報酬の減額分を役員借入金で充当するわけですので、減額できる役員報酬の分が大きければ大きいほど、役員借入金が減っていくスピード(つまりは役員借入金が解消していく)が早くなります。
役員借入金がそれなりに計上されていて、役員報酬の金額がある程度設定されているのであれば、検討していただきたい選択肢になります。
2. 債権贈与による分散
もう一つの債務免除以外の対策としては債権贈与があります。
役員の立場で見ると会社への貸付金ですから債権となります。この債権を後継者などに贈与しておくという選択肢です。
親族の後継者がいる場合にはこちらも検討してもらったほうがよいのは、役員借入金を当座ではありますが分散することで、その役員の相続財産としての役員借入金を減らせるからです。
ご提案として多いのは、210万円の役員借入金の債権贈与をして、贈与税は10万円かかりますので、その10万円を贈与を受けた人が会社から返済を受ける形で引き出して納税をするという流れです。
210万円の債権贈与→贈与税10万円→その10万円を会社から受贈者が引き出して納税→役員借入金の残高は200万円に、という金額的な流れをとることで、受贈者は資金的な持ち出しがない状態で贈与により債権が移転できます。
この債権贈与と前段で触れた役員報酬の減額を組み合わせるのも効果的です。
役員借入金を贈与された後継者の方が役員報酬を取っているのであれば、その役員報酬を減額して、その分を贈与された役員借入金で充当するという組み合わせを取ることで、役員借入金の分散と減少の効果が二重取りできます。
まとめ
役員借入金の債務免除は手っ取り早い解決策ですが、「返してもらえなくなる」という大きなデメリットがあります。
これに対して、役員報酬の減額による返済や債権贈与による分散といった対策を活用することで、役員借入金を減らしながらも将来の回収可能性を残すことができます。特に債権贈与は相続対策としても有効であり、役員報酬減額との組み合わせによって、より効果的な役員借入金対策を実現できます。
各企業の状況に応じて最適な対策を選択し、継続的に役員借入金の管理を行うことが重要です。