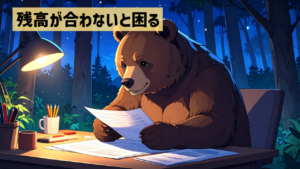漫画家・同人作家のかたが法人化を検討する際には著作権のやり取りについて注意しましょうという記事を以前に書きました。

今回はさらに一歩踏み込んで著作権の税務関係について触れてみます。
法人化の際の著作権の取り扱い
漫画家・同人作家のかたにとって法人化は一定のタイミングで検討したり税理士側から提案があるケースが多いです。
イメージだと年間売上が3,000万円を超えてくると税理士事務所からも提案があることがあるようで、本当に法人化しても大丈夫そうか、というスポット相談は去年から増えています。
私は漫画家・同人作家の方は法人化しなくてもある程度、社会保険料対策などもできるため法人化をお勧めしていません。
その理由の一つでもあるのが著作権の取り扱いです。
法人化するときには作家個人に帰属している著作権を法人側に移すのかどうするのか、というのが税務的な検討ポイントになります。
パターンとしては「譲渡」、「貸し付け」、「何も手当てしない」の3つです。それぞれどのような対応になるか見ておきます。
譲渡について
個人から法人に対して著作権を譲渡する形になります。
個人側では著作権を譲渡する際には総合課税(5年以内でも長期譲渡所得)となり、課税対象になる点に注意が必要です。
法人側では対価の支払いが必要となりますが、その著作権の使用料等の対価を得ることができます。
著作権は非減価償却資産とされているので減価償却により経費化することはできません。ここは個人的には少し疑問を感じるところで、著作物からの収入は時の経過により減少していくことが多いです。
まれに過去作がヒットするということもありますが、基本的には得られる収入は減少していくにもかかわらず経費になる部分がないというのは収益費用の対応としてはズレが生じているように見えます。
貸し付けについて
個人から法人側に著作権を貸し付ける、ということも一部で行われているようです。
個人側に著作権が帰属した状態ですので、法人側から著作権の貸付の対価を得ることになります。
法人側は借り受けた著作権を管理運営してそこから得られた対価のうちから管理料を引き、残りを個人に渡すという流れをとります。
不動産の部分が著作権に置き換わった形となりますが、不動産管理会社をイメージしてもらうとわかりやすいです。
不動産管理会社のパターンでもそうですが、管理料の設定金額が税務調査等で指摘されることがあります。著作権の管理だけだとそう高くは設定できないと考えられます。
あと法人側から個人に渡す際に源泉徴収の必要があるのでは、というのが検討ポイントです。
そのため貸し付け方式をとると法人側にそれほど所得移転ができなさそう、というのが私の個人的な考えです。
何もしない場合
何らの手当てもなく法人を設立して著作権の使用料や印税・原稿料を法人側で受け取っている状態です。
この場合は一見すると何も問題がなさそうに見えますが、税務調査になったときに行為計算の否認なども含めて所得税や消費税の修正等を指摘される可能性があります。
想定される指摘事項としては著作権が移転していないから個人側で課税する、といった内容です。
この場合は個人側で申告のし直し(所得税や消費税)となる可能性があり、著作権という収入源がある以上は何らの手当てもしていないとかなり苦しい戦いになる可能性があります。
特に「所得の帰属」つまり所得が誰のものか、という問題がでてきます。著作権という資産から得られる所得は資産保有者に帰属する(所得税法基本通達12-1 資産から生ずる収益を享受する者の判定)と考えられるとも言えます。
その資産の名義人に帰属するというのが原則的な取り扱いですので著作権について何らの手当てをしていない場合は著作権の所有者であり名義人は作家個人と考えられますので、法人に著作権から得られる所得を付け替えているだけと指摘されることも想定できます。
著作権の時価
著作権の時価についても再考しておきます。
一般的に税務上の時価というのは第三者間の取引における売買価額を指すことが多く、市場がある場合にはその市場価格が参考とされます。
不動産や株式など第三者間で売買があった時にはその取引価額が時価とされますので問題にはなりづらいです。
親族間などの場合には価格調整がされている可能性があり、第三者との取引ではないという点が注意点となります。
法人と著作権のやり取りをする場合には、その個人の作家や親族が株主になっている法人とのやり取りです。
いわば同族会社とのやり取りですので純粋な第三者との取引とはみなされません。
そういう時にはやはり取引価格の問題が出てくることが税務の現場では多くあり、著作権の取引価格も同じようにみられる可能性があります。
ただし、著作権の売買は市場がなく取引事例も一般に広く認知できるものではないと考えられるため、相続税評価額などを参考に計算するほかないとも言えそうです。
逆に相続税評価額でやり取りしているのであれば問題にはしづらい、ともいえると考えています。
まとめ
漫画家・同人作家が法人化する際の著作権のやり取りについて個人的な見解も含めて書いてみました。
税務調査や裁決・裁判例などは今のところはなさそう(表に出てきていないだけの可能性もあります)ですが、税務上の注意すべき点が多いので慎重に判断しておきたいところです。